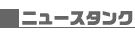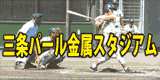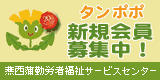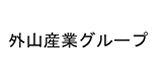羽生善治九段が三条市合併20周年記念で講演 棋士の思考プロセスから長考やAIについても (2025.7.5)
新潟県三条市の合併20周年を記念した将棋界のレジェンド、羽生善治九段(54)の講演会が5日、三条市立大学で開かれ、三条市立大学体育文化会館で開かれた。会場の300席は満席となり、羽生九段は自身の経験から導き出した思考法から、AIとの共存、時代を超えて受け継がれるべき人間の営みの価値まで、ユーモアを交えながら深く語りかけた。

羽生九段は、8年前の2017年11月に三条市・嵐渓荘で行われた第30期竜王戦七番勝負第4局で渡辺明九段と対戦、勝利した。また、三条市在住の駒師、大竹竹風さん(81)作の将棋駒「竹風駒(ちくふうごま)」を愛用している。
講演に先立ってあいさつした滝沢亮三条市長は、羽生九段が合併20周年に花を添えてくれる」と感謝。3日行われた藤井聡太王座への挑戦者を決める王座戦挑戦者決定戦で羽生九段が敗れた対局にふれた。「終盤の最後の4四桂でそれまで均衡を保っていたのを勝負にいった手は本当にすばらしいと思った」、「大変、勇気をもらった」と将棋に明るい滝沢市長はハグ九段の対局に敬服した。
市長就任前に行われた嵐渓荘での竜王戦に羽生九段は勝利したことから「三条市は好きなまちなんじゃないかなと思う」と推察。「今だから申し上げるが、仕事をしているふりをしながらパソコン画面はずっと対局のようすを開いていて、評価値が変わるごとに一喜一憂していた」と明かし、会場の将棋ファンを笑わせた。

棋士の思考プロセスは「直感」、「読み」、「大局観」の3つの柱
羽生九段の講演は、棋士の思考プロセスの解説で始まった。羽生九段は、複雑な局面で次の一手を導き出す思考を「直感」、「読み」、「大局観」の3つの柱で説明した。
まず働くのが「直感」。これは当てずっぽうではなく、過去の膨大な経験や知識が瞬時に集約されたもの。写真のピント合わせのように、無数の選択肢の中から「ここが急所ではないか」と数個に絞り込む作業と巧みな例えで説明した。
次に「読み」。絞り込んだ手を元に十数手先までをシミュレーションするが、その可能性は爆発的に増える。「3つの候補手から10手先を読むと、可能性は3の10乗、約6万通りにもなる。これをすべて読むのは現実的ではない」。

そこで重要になるのが「大局観」だ。これは思考のショートカット。全体の方向性や戦略を見極め、無駄な読みを省く力である。「木を見て森を見ず」という言葉があるが、その逆で、森全体を見て、どの木に焦点を当てるべきか判断する。
「長考に好手なし」で4時間の長考が5秒で考えた手と同じだったことも
よく質問される「長考に好手なし」という格言については、最初の30分ほどで論理的な思考はほぼ尽きる。その後の時間は、どちらの選択肢を選ぶべきかという心理的な葛藤や不安と向き合う時間なのです」と内面を明かした。自身が4時間もの長考の末に指した手が、実は5秒で考えた手と全く同じだったというエピソードには、会場から驚きと笑いがもれた。
「なぜ棋士は長い棋譜を記憶できるのか」という長年の疑問にも、明快な答えを示した。歌や音楽を覚えるのと同じ仕組みで、物語や流れ、つまりフォーマットがあるから記憶できると解説した。

ルール覚えたての幼稚園児の対局は全然、予想する手を指してくれず、意外性の連続で覚えられなかった。駒をすしに置き換えた盤面も覚えられなかった。記憶が単なる暗記ではなく、文脈や関係性の理解に基づいていることを示した。
人間がAIから学ぶ時代、背景の意味を人間が解釈し主体的に学ぶ姿勢が重要
近年、人間をしのぐ強さを見せる将棋AIについては、かつてのAIは計算量とデータ量で強くなる「ブルドーザー方式」だったが、近年は機械学習によって大きく進歩したと説明した。とくに相手の手を予測する評価の能力が向上したことが大きな変化だと指摘。AIの学習方法や人間の棋士がAIから学ぶ現状についてもふれ、テクノロジーの進歩は人間の能力を引き上げるために活用されるべきだと述べた。
データと計算力という『足し算』で強くなりましたが、今のAIは自ら学習することで強くなる。もはや人間がAIから学ぶ時代」と断言。ただし、「AIが出した答えをうのみにするのではなく、その背景にある意味を人間が解釈し、主体的に学ぶ姿勢が重要です」と、AIとの新しい共存の形を提言した。

将棋界の人間関係の特徴として、年齢差を超えたコミュニケーションがあり、自身が16歳の時に明治生まれの大先輩と朝まで感想戦をした思い出を紹介。将棋を指さないが観戦を楽しむ人が増えているのは自然な流れで、長い歴史をもつ文化や伝統を次世代に継承していくことの重要性を強調し、人と人とのつながりの大切さも語った。
羽生九段の色紙は「一歩千金」、将棋で非常に重要な数字の81歳になった「竹風駒」の大竹竹風さんも「歩のごとくがモットー」
講演のあと抽選に当たった3人に羽生九段が将棋の格言「一歩千金」を書いた色紙をプレゼントした。「一歩千金」は歩兵でも場面によっては金将よりも勝ちがある、重要な意味をもつことを表している。
大竹竹風さんは最前列で羽生九段の話を聞いた。竹風駒を通じて羽生九段と親しくなった。竹風駒はプロ棋士の対局でも使われる。この日の講演では、長考と直感の話がいちばん大竹さんの心に残った。

「わたしにも直感が仕事のなかにある。直感がなければだめ」と大竹さん。「わたしは職人だから直感をすごく意識する。木を駒の大きさの四角に切ってて全部並べて、上から見てパパパパと1組、取る。それが直感で取る。またあとで並べ変えるが、最後にこれで決まりっていうのは、いちばん最初の直感に戻る。仕事は違うけれども、同じことを思っているとつくづく思った」と感心していた。
81歳になった。「81」は将棋で非常に重要な意味をもつ。将棋盤のます目の数で、数え年で81歳を「盤寿」と言う。「歩のごとくが、いちばんの自分のモットー。一気にいくんじゃなく、一歩一歩、積み上げていくということ。81歳になるのは将棋界ではいちばんのお祝い」と、羽生九段と自身を重ねてあらためて羽生九段の言葉をかみしめていた。
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com