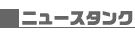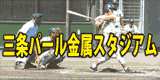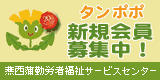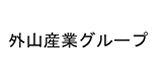9日は中央商店街で三条マルシェ 恒例の鍋グランプリも (2025.11.8)
9日(日)午前10時から午後3時まで新潟県三条市で「第三回三条マルシェと秘密の空き家」が開かれる。歩行者天国にした中央商店街の目抜き通りを舞台に38店舗が出店。冬のマルシェで恒例の「第10回鍋グランプリ」も開かれる。

丸井今井邸角の「本町二・三丁目」交差点から昭栄大橋下まで約350メートルが歩行者天国になる。出店数の内訳は食べ物・飲み物17、雑貨・クラフト9、PR他10、半分のスペースに出店するハーフ2で、38店舗のうち7店舗が初出展となる。
第10回鍋グランプリは、1杯400円の鍋チケットを買って好きな鍋に投票。優勝店舗には諏訪田製作所の特製トロフィーと副賞が贈られる。3枚つづりの鍋チケットには、抽選券も付く。
ふだんはカレー、ラーメン、焼き肉、和食などを提供する9店舗が出店し、うち1店舗は初出店。福島県南会津町も郷土料理のくじら汁でエントリーする。
今回も子どものおしごと体験「三条マルシェギルド」を用意。市立第三中と月岡小がキッズ出店でコラボし、12店を企画、運営する。
三条マルシェで日本デザイン学会第1支部大会

また今回、ユニークなのは、日本デザイン学会第1支部大会とのコラボレーションで、8日、9日の2日間、中央商店街の旧アサマ家具で開かれる。第1支部は北海道・東北エリアだが、今回の大会は第3支部の北陸・東海エリアの新潟では初開催となっている。
「<あきない>デザイン」をテーマに、地域に根ざした実践と学術研究が融合するユニークな試みとして注目される。「あきない」は「商い」(人・モノ・コトを循環させる日常のデザイン行為)と「飽きない」(持続的に生み出される知の現場)、そして収穫の「秋」をかけている。
大会のねらいは、産業デザインのロジックだけでは語り尽くせない、市民による営みと生活世界の知を実践の現場である三条マルシェを通してとらえ直すこと。専門用語が飛び交う情報交換だけでなく、実際にデザインを体感することを重視。身近な実践としてのデザインを、学問として言語化、理論化することを目指すし、専門家と一般の人の距離を縮め、同じ目線で活動できる場を創出する。

8日は準備運動で、9日は一般公開。8日はあえて目的をもたずに中央商店街を散策するフィールドワークでまちの課題の抽出や休眠状態のマルシェ備品のリ・デザインなどを行った。まちの課題では「ドーナツ化は悪いこと?」や「町の違和感を魅力と感じるのはなぜか」があがった。
9日は三条マルシェの準備から参加。全国から集まる学生や研究者が会場設営からアートマーケット・展示、研究発表大会のポスター発表、シンポジウムなどを行う。
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com