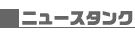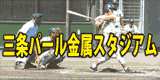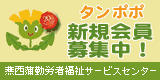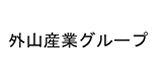【三条祭り大名行列】新社殿20周年、初めて女性やっこ登場、三条中央商店街アーケード撤去後初の大名行列 (2025.5.15)
新潟県三条市の八幡宮(藤崎重康宮司)の春季例大祭、通称「三条祭り」は、14日の宵宮祭に続き、15日は例大祭に続き御神幸祭の神輿渡御(みこしとぎょ)に伴う十万石の格式を誇る大名行列が市中を進んだ。ことしは八幡宮が新社殿になって20周年。初めて女性のやっこがお目見えした記念すべき年で、三条中央商店街のアーケードが撤去されてから初めての三条祭りともなった。

三条に八幡宮が創建されたのは885年(仁和元年)3月15日。大崎にあったが、1599年(慶長4)に現地へ遷宮された。当時は八幡宮の誕生日の3月15日に春季例大祭が開催されていたが、太陰暦が太陽暦に変わったのをきっかけに1874年(明治7)から5月15日になった。
1357年(延文2)から神輿渡御が行われ、今のような形の大名行列になったのは1822年(文政5)に三条の領主、村上藩主内藤信敦が京都所司代に就任したのを祝って始められたとされる。

鉄棒、露払、やっこ、天狗、神輿。押槍(おしやり)など続き、行列の最後尾には、当時の村上藩10万石を表す10本の押槍が並び総勢220人以上で構成する大名行列だ。
大名行列の人員確保から当日の行列組立、運行管理を行う三条祭り若衆会をはじめ、やっこを演じる三条先供(さきとも)組合、てんぐを拝命する三条導祖神会、はやしを奏でる八幡宮囃子方(はやしかた)組合、三条傘鉾(かさぼこ)振興会、着付方、さらに三条エコノミークラブ、三条商工会議所青年部、燕三条青年会議所といった地元青年団体が人手を出し、多くの団体が力を合わせて行っている。


午後1時前の大名行列出発にあわせて各団体はそれぞれ準備を整えて八幡宮に集結。拝殿で払いを受けてから境内で行列を組み立て、吉井直樹祭典委員長が「新社殿になって20周年になる。記念の年になるのでしっかりといい行列をしていきたい」とあいさつしてから、大名行列が境内入り口の太鼓橋を渡って出発した。
てんぐが二本歯の高げたをはいて立ち上がると、2メートルを超える身長のように見えるので、見物客からはどよめきが起こった。てんぐは力を込めて鉾(ほこ)を地面に打ち付け、大きく足を振り上げてはおろし、カシャン!、カツン!と大きな音を立て、邪鬼を踏みしめながら進んだ。
昨年から大名行列の八幡宮囃子方と三条先供組合の女人禁制が解除された。八幡宮囃子方は昨年初めて女性が参加し、ことしも13人の女性が参加した。


三条先供組合は昨年は参加を希望した女性がいなかったが、ことしは保育士の倉橋由佳さん(39)と第二中学校3年の鳥羽一花さん(14)の2人が初めて女性のやっこを演じた。
やっこは2人1組になって道具を投げ渡しながら進む。倉橋さんは天目槍(てんもくやり)を担当。道具の投げ渡しに成功するたびにひときわ大きな拍手でわき、沿道を盛り上げた。
出発直前は険しい表情だったが、「風がすごく影響するんだなと思って。でも楽しくできてます」とにっこり。「わー、すごいみたいな、女の人、頑張れみたいな感じだから、応えながらやってます」と声を弾ませた。

鳥羽さんは単独で長柄を回して投げ上げたり、払ったりのパフォーマンス。「周りのひとがいっぱいいて緊張するのもそうなんですけど、盛り上げてくれてすごく楽しい」と言い、「首の技のときにすぐ足を引いて待つという所を改善したい」と向上心をもちながら取り組んでいた。
大通りを進む大名行列の先を木場神楽保存会が獅子神楽の門付けに回り、祭りムードを盛り上げた。

さらに裏館小学校の4年生から6年生が裏館小4年生から6年生まで79人が大名行列番外「子供神輿」行列を行った。行列の先頭はみこしを担いだ5年生75人、続いて自作のドラえもんと大阪万博のキャラクター「ミャクミャク」の2つの傘鉾とともに歩く4年生73人、しんがりは太鼓と篠笛で演奏する「車切り」の6年生79人が大通りを進んだ。
昨年、大通りに面した三条中央商店街のアーケードが解体撤去された。アーケードが無くなった三条中央商店街で初めての大名行列。これまでアーケードに紅白幕を下げていたので、独自で紅白幕を下げた一部の店舗を除いて紅白幕が無くなったのは寂しかった。

しかし逆に言えばアーケード建設前の商店街に戻ったわけで、アーケードが無くなった分だけ大通りは格段に広く感じ、新たに模様替えした舞台での大名行列ともなった。
また毎年、行われている子ども大名行列の参加経験者5人がやっこに参加。子どものころの体験が今の大名行列につなっがっていた。


























三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com