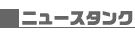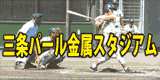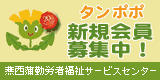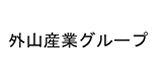「このような神賑わい行事は今年を最後にしたい」 神輿行列の人員確保が限界に達したと燕・戸隠神社の星野宮司が春祭りを前に所感 (2025.5.16)
新潟県燕市宮町、戸隠神社の星野和彦宮司は、17日、18日と行われる春季例大祭に向けて所感を寄せた。このなかで星野宮司は、氏子の参加がなく借り物の祭礼行事を「神賑わい行事は今年を最後にしたい」考えを示した。

星野宮司が指摘するのは、神輿(みこし)行列。所感にあるように少子高齢化とドーナツ化現象で、戦後は2,000戸あった氏子町内が今では400戸に激減した。そのうち戸隠神社とかかわりがあるのは200戸ほどに減ってしまった。
神輿行列はかつて「大名行列」と称した。やっこも存在したが、必要な人手を確保できず年々、規模を縮小。神輿も担げず、台車に載せて運ぶ。
人手の多くはシルバー人材センターや外国人研修生でまかなっているが、氏子の参加がないのでは、神輿行列の基本的な意味を失ってしまい、形だけが残っている。
来年は次代を背負う若者とともに氏子町内にとらわれない今の時代にふさわしい春祭りに

一般に祭りの行事は神社を崇敬する氏子らが組織をつくって行うが、祭典委員長を欠いて久しく、星野宮司がほぼすべてを担当している。氏子の参加がない借り物の行事では「続ける意味がない。神様にも申し訳ない」。
近年は人員確保に綱渡りの状況で「もはや限界を迎えた」。そこで「このような神賑(にぎ)わい行事は今年を最後にしたい」と神輿行列の継続を断念せざるを得なくなった。
一方で昨年、神社のおひざ元の宮町に複合施設「まちトープ」がオープンし、若者が集う場所として定着している。その動きと連携して「次代を背負う彼らと共に氏子町内に囚われない、今の時代にふさわしい『神人和楽(しんじんわらく)』の祭礼行事と賑わいを模索したい」と来年は新たな春祭りを練る考えだ。星野宮司の所感は次の通り。
令和7年春季祭礼 宮司所感
燕地区唯一の神賑わい行事が行われる戸隠神社の春のお祭りが近づいてきた。街のあちこちに「萬燈」のポスターが掲げられている。市民の楽しみである春のお祭りが天候に恵まれ多くの人出になることを期待している。
かつては燕や西蒲原の中心市街地としてにぎわった戸隠神社の氏子町内であるが住宅や工場の郊外への移転と急激な少子高齢化、そして過疎化の波により祭り行事の担い手が不在となってしまった現状を見ると、過去のような賑やかな祭禮行事を氏子町内に望むのは無理である。戦後二千戸余りあった氏子町内は四百戸に徹減してしまったのである。
燕市内10町内だけで構成される戸隠神社の祭禮行事のうち神輿渡御に関わる行列は、近年は人員確保に綱渡りの状況であり、もはや限界を迎えた。
幸いにして、万灯町内や御神楽町内も厳しい町内事情がある中で、関係者の将来を見越した運営努力により、今日まで父祖の残した伝統行事を守り伝えて来ていただいた。これら関係者は本番当日に向けて、年明けから連日の会合や稽古を続けてきている。この努力に対しては敬意を表している。
「歴史伝統は守り伝えるもの。しかし時代と共に移り変わるもの」
残すためには何を変えるのか、そこのバランスを考え今後の祭禮行事を見直さなければならない時と考えている。たとえ、神賑わい行事に人出が多くとも、祭り行事は単なる見世物ではない。氏子の参加がない祭禮行事、借り物の祭禮行事では、続ける意味がない。神様にも申し訳ない。このような神賑わい行事は今年を最後にしたい。
近年、神社のおひざ元、宮町に若者が集える施設が誕生した。次代を背負う彼らと共に氏子町内に囚われない、今の時代にふさわしい「神人和楽」の祭礼行事と賑わいを模索したい。
世界は今、トランプアメリカ大統領の関税政策により右往左往している。国内に目を向けると物価の高騰などで厳しい生活を強いられている。神代から伝わる豊葦原(とよあしはら)の瑞穂(みずほ)の国はコメ不足である。食糧危機に直面している農業国日本の今の姿は尋常ではない。
現状打破のために岩戸開きの神々に、真剣に「祈ること」が宮司に課せられた最大の使命である。正念場を迎えた今年の春季祭礼である。心して望みたい。
戸隠神社宮司星野和彦
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com