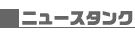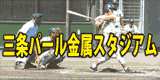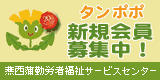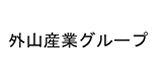8月4日の「はしの日」にはし供養 日本人の心のはしに感謝 (2025.8.4)
「は(8)し(4)」の語呂合わせで「はしの日」の8月4日、ことしも新潟県三条市の八幡宮(藤崎重康宮司)ではし供養祭が行われ、使い古したはしを焼納して、食を支え、生活に欠かせないはしに感謝した。

はし供養祭ではしをくべる県央食品衛生協会三条支部の関支部長
新潟県三条市の食品関係事業者などでつくる県央食品衛生協会三条支部(関能宏支部長)の主催で毎年行われている。はし供養祭は1975年に民俗学研究者が「はしを正しく使おう」と提案して始まり、東京・日枝神社の箸(はし)感謝祭が有名。三条市ではその3年後の78年に三条割烹組合主催で始まり、翌79年から食品衛生医協会が主催に。7.13水害のあった2004年とコロナ禍の2回、休み、ことしで45回目となった。

拝殿で神事
藤崎宮司は神事を行ったあと「食べるということは生きていくうえでいちばん基本。それに必要なはし。店ではしの持ち方がおかしい人がいたら、さりげなく指導してほしい」と作法の向上も願った。

焼きそばとかき氷のふるまいに行列
このあと拝殿の外に出て会員らが持参した使い古した割りばしなど約500ぜんをかがり火台にくべた。関係者に続き、一般の来場者も手を合わせた。
このあとはお待ちかねの400人分を用意した焼きそばとかき氷のふるまいと、ミニ縁日のスーパーボールすくいや水ヨーヨー釣りが店開き。手洗い練習スタンプを手のひらに押してせっけん液と水で落とす手洗い教室も行った。

手洗い教室
ふるまいの始まった午前11時の三条市の気温は33.3度の猛暑。ふるまいに順番待ちの行列ができたが、連日の厳しい暑さに外へ出るのもおっくうになったのか、来場者は例年より少なめ。それでも、はしを燃やすという特別な行事にふれ、焼きそばにかき氷をたべてひとときの涼を味わっていた。
■Copyright (C) kenoh.com Allrights Reserved.
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com