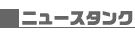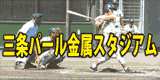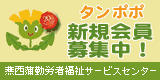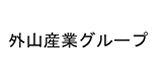三条凧合戦がタイへ 11/29・30「シラチャ日本祭り」に参加し「三条凧揚げ太鼓」を初披露 (2025.11.18)
新潟県指定無形民俗文化財「越後の凧合戦習俗」のひとつ、三条市で伝承される「三条凧(イカ)合戦」が、ことしはタイへ海外遠征する。三条凧協会(須藤謙一会長)は11月29(土)、30(日)の2日間、タイ中部のチョンブリー県シラチャ市で開かれる「シラチャ日本祭り」に参加。今回は模擬凧合戦や凧揚げ体験に加えて「三条凧揚げ太鼓」の演奏にも初挑戦し、メニューを増やして三条の凧文化をさらに積極的にPRする。

若手に「世界につながる凧文化」を体現
三条凧協会は、海外事業として2022年にアゼルバイジャン、24年に台湾へ遠征している。12日行った事業の記者会見で川口純平事務局長は「日本文化に関心のある人に見てもらうことが何より重要だと考え、世界各地の日本関連の祭りを探して自ら連絡した。主催者から、すぐにぜひ来てほしいと返事をいただき、事業が実現した」と経緯を話した。
結城靖博副会長は「三条の凧合戦が海外で高く評価されていることを、まず地元の人に知ってほしい。凧合戦を頑張っていれば、将来は三条を、そして日本を代表して海外で披露できるという後ろ姿、背中を若い世代に見せたいとやってきた」と思いを語った。
三条凧協会はこれまで、東日本大震災の復興を願う福島県双葉町での凧揚げや、群馬県前橋市の上州空っ風凧揚げ大会への参加など、国内外での交流事業を重ねてきた。三条六角巻凧は骨組みを外すとコンパクトに収納できて持ち運びしやすく、海外遠征にも適している。

シラチャ日本祭りは、日本企業が数多く進出するシラチャ市で2009年から続く現地日本人会が主催するビッグイベント。昨年は2日間で約2万4千人が訪れている。日本食や物販ブース、一青窈など日タイ両国のアーティストによるステージもある。
3つの企画「模擬凧合戦と凧揚げ体験」「六角巻凧の絵付け体験」「三条凧揚げ太鼓凧ばやし」
協会加盟の凧組から揚げ師14人が参加し、カメラマン1人が同行する。27日に燕三条駅を出発し、バンコク経由でシラチャに3泊。祭り後は会場片付けや荷物の発送作業を行い、バンコクに1泊して12月3日に帰国する。
会場では「三条凧合戦 in Thailand」と題して3つの企画を展開する。一つ目は、会場内広場での模擬凧合戦と凧揚げ体験。参加する14人の揚げ師が、現地の空で糸を絡ませ合う迫力ある合戦を披露するほか、子どもからおとなまで参加できる凧揚げの体験コーナーを用意する。
二つ目は、須藤凧屋8代目でもある須藤謙一会長の指導による六角巻凧の絵付け体験ブース。和紙に絵を描き、三条独自の凧文化にふれてもらうとともに、ブース内では三条凧と合戦の歴史をタイ語で紹介する展示も行う。

三つ目は、2日目のメインステージで「三条凧揚げ太鼓」を披露する。「三条凧揚げ太鼓」は、三条市の和太鼓のグループ、三小相承会が「三条凧ばやし」を膨らませてアレンジした和太鼓や笛、唄、踊りで構成される演目。それを数分の短縮版で演奏する。
協会内に「三条凧ばやしクラブ」を立ち上げて本番まで2カ月間の猛練習
今回の海外事業を機に協会内に新たに「三条凧ばやしクラブ」を立ち上げた。三小相承会の長野源世総監督が指導にあたり、和太鼓やたる太鼓などを持ち込み、計12人編成で臨む。
笛の経験者や1年前から笛を始めた人もいるが、ほとんどのメンバーが初挑戦。9月の終わりに練習を始めてまだ2カ月足らずだが、個人練習に励み、十分に聞いてもらえるほど長足の進歩を遂げた。
長野さんは「三条凧揚げ太鼓は“聞いたことがある”ではなく、“三条なら誰でもたたける”くらいになれば、それは三条の宝になる。短期間の練習だが、何万人の前でも胸を張れる仕上がりになってきた」と文字通り太鼓判だ。

凧や天気に左右されない太鼓演奏で発信力アップ
凧揚げは風や天気に左右される面も大きい。結城副会長は「雨や無風で思うようなパフォーマンスができず、悔しい思いをしたこともあった。凧合戦とあわせて凧ばやしを身につけることで、どんな状況でも三条の文化を届けられるもうひとつのコンテンツになる」と意義を話す。
協会はシラチャの行政機関やシラチャ日本祭り実行委員会に、今回の事業を記念したオリジナル凧3枚を寄贈する。すでに三条六角巻凧や太鼓一式も現地へ発送済み。「三条から飛び立った凧と太鼓の響きが、タイの人たちの記憶に残り、三条や新潟、日本への関心につながってほしい」と期待している。
- sriracha.japan.festival - シラチャ日本祭り - Instagram(新しいウィンドウで開く)
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com